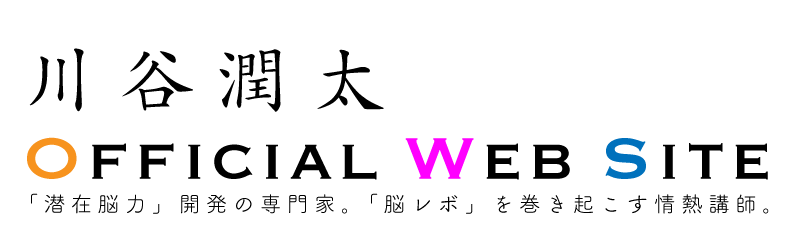現在多くのスポーツ(教育)指導者が、その指導について頭を悩ませています。
それは…
・これまでの指導のあり方が、根本的に見直されているから。
・部活動の練習時間減で、指導時間に限りがあるから。
・親(保護者)からの圧力が厳しい(親がいちいち出てくる)。
などなど。
それらを踏まえた、これからの時代にふさわしい「指導のセオリー」(科学的根拠のある指導)があれば良いのですがね!
…ということで「スポーツ指導のセオリー」、ご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スポーツ指導のセオリー①
みなさんはスポーツ(運動)に上手・下手があるのはなぜだと思われますか?
遺伝的(天性)な原因によるものなのでしょうか?
それとも生まれ育った環境(学習)によるものなのでしょうか?
これまでの研究でわかってきたことは、身体的障害がない限り、スポーツ(運動)の上手・下手は遺伝的なものではないということです。
人間は経験や知識による学習で成長する動物です。
生まれ育った環境で経験し、学習したことが大脳で記憶され、そしてその人の個性となるのです。
よってスポーツに上手・下手があるのは、単に脳の使い方(プログラム)が悪いだけなのであって、正しい使い方(プログラム化)をすれば誰でも短期間に上達することができるのです。
みなさん(特に指導者)には、このような生理学的事実があるということを知っていただきたいのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それではその生理学的事実、スポーツにおける脳の学習システムについて解説します。
スポーツをする初歩段階は「見よう見まね」です。
初心者は他人がプレーしているところを観察して、その真似をすることからスタートします。
人間が運動するためのシステムは…
大脳から筋肉までの随意運動または意識運動(初心者レベル)と
小脳から筋肉までの小脳反射運動または無意識運動(熟練者レベル)
そして脊髄から筋肉までの反射運動に分類することができます。
スポンサーリンク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スポーツにおいて大切なことは、常に無意識運動をすることです。
意識運動のように大脳で考えて運動をしていては、反射スピードが大幅に遅れるからです。
小脳は運動の中枢脳であり、身体の動きを微調整して、運動を正確に円滑に行わせる働きをしています。
しかし初心者のうちから無意識運動はできません。初心者のうちは意識して運動しなければならないのです。
まず意識的に行う運動(随意運動)を続けていると、大脳の運動皮質から小脳の赤核という部分に伸びている神経回路が繋がり始めます(これを可塑性と言います)。
そこで小脳が運動パターンを記憶します。
コントロールを気にせずにボールを打ち続ける練習や素振りをすることで、その運動をするための最適な回路を、小脳の中に組み立てて記憶してくれるのです。
スポーツに反復練習が必要なのはこのためなのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように誰でもがこのプロセスを経るのであれば、上手・下手の区別がなく、すべての人が素晴らしい運動能力を発揮できるはずなのですが、残念なことに脳にはもっと複雑な働きがあり、その働きのために運動学習に大きな差が生じてくるのです。
一般的に運動神経の発達している人は、反復練習により次第に上達していきます。つまり無意識に身体で覚えていっている、学習しているのです。
日常生活の中でこのような無意識下の学習の占める割合はとても大きいのですが、ただ無意識で運動したり行動しているので、多くの人が気付かないのです。
人間の行動は無意識に学習されたことで、そのほとんどがコントロールされていると言えます。
― 続く ―
スポンサーリンク